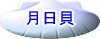○ 青笹の開けて雪代山女魚かな
あおざさのあけてゆきしろやまめかな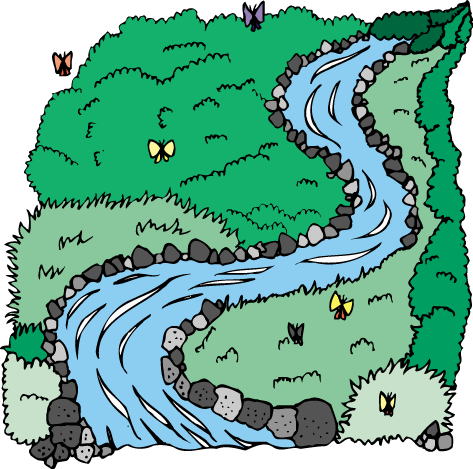
季語・雪代または雪代山女魚 春
| 雪代とは雪どけの水のことで、渓谷でそのころに捕れた山女魚が青い笹の葉に包まれて届いたのです。 |
○ ものの芽の力の満ちて尖りたる
もののめのちからのみちてとがりたる
季語・ものの芽 春
| ものの芽とは草木の芽を広くさします。みな先が尖って出てきますね。 |
○ 蝶の来てかたかごの花揺らしをる
ちょうのきてかたかごのはなゆらしおる
季語・蝶およびかたかご 春(季重なり)
| かたかごの花はカタクリの花の古名。春の舞姫と別名のあるギフチョウが早春の里山で紫のカタクリの花に飛んで来て蜜を吸っています。 |
○ 湧水に揺らるる砂子花山葵
わきみずにゆらるるすなごはなわさび
季語・花山葵 春
| 里山の湧き水は透明で水底に砂粒が浮き沈みしています。そばには山葵の群生が白い花を咲かせています。句の構成は五七/五と切れる二句一章。 |
○ 水口の切られし畦の菫かな
みなくちのきられしあぜのすみれかな
季語・菫 春
| 水口とは田へ水を引く口のことで、畦に水口が切られるのも稲作のはじまる早春の農村の風景。固められ直した田の畦にすみれが咲いていたという小景。 |
○ くつつきて夢重ねたる子猫かな
くっつきてゆめかさねたるこねこかな 
季語・子猫 春
| 重なり合って寝ている数匹の子猫たちが、そのしあわせな夢も重ね合っているように見えました。 |
○ 陽だまりの猫の大の字春の土
ひだまりのねこのだいのじはるのつち
季語・春の土 春
| 猫はとにかくあたたかい日だまりが好き。大の字になって寝ています。春の土も暖かい日射しをあびて黒くかがやいています。句の構成は五七/五と切れる二句一章。 |
○ 草萌や濡れてこの世にあらはるる
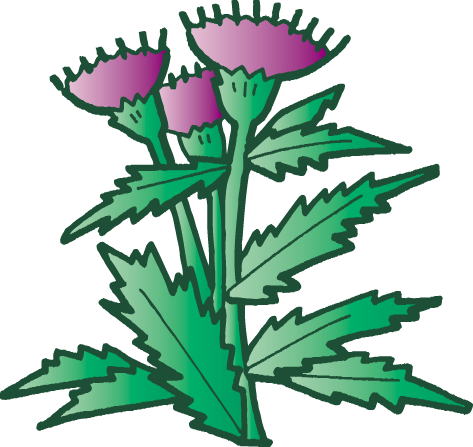
くさもえやぬれてこのよにあらわるる
季語・草萌 春
| 草萌は早春に草の芽が土から萌え出ること。赤子の出生も(羊水に)濡れて、この世に現れるのですね。句の構成は五/七五と切れる二句一章。 |
○ 争そうてまた睦み合ひつばめの子

あらそうてまたむつみあいつばめのこ
季語・つばめの子=燕の子 春
(なお燕だけでも春の季語)
| 親鳥が餌を運んでくると取り合って押し合い、へし合いしますが、また仲良さそうにくっつきう燕の巣の中の様子。 |
○ また潮の曳いてゆきたる月日貝
またしおのひいてゆきたるつきひがい
季語・月日貝 春
| 春の浜辺でゆったりとした潮の満ち引きに揺すられながら色褪せた月日貝の貝殻が行き来しています。あたかも月日の経過も象徴するように。 |
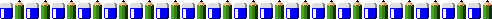
 |