○ 葉桜や略歴といふ括り方 中原道夫・選 「銀化」 掲載
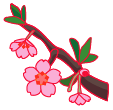
はざくらやりゃくれきというくくりかた
季語・葉桜 夏
桜で花が散り、若葉が出たものが葉桜です。「花は盛りをのみ見るものかは」萌え出た若葉もそれなりの美しさです。また人間が学歴などのラベル付けで評価されることに不満なんですね、たぶんこの作者は。
俳句としての構成は「取り合わせ」という方法です。つまり「葉桜」と「略歴といふ括り方」にはなんの直接の因果関係もありません。詩的に響き合うととれるかで評価は分かれます。
新潟市で開催されている「とねりこ句会」の第一回でお仲間から共感の最多票をいただき、句意を理解していただけたことが最高にうれしかった句です。 |
○ 留守の間に土と筍置きてあり 黛 執・選 「春野」 掲載

るすのまにつちとたけのこおきてあり
季語・筍 夏
用事で出て帰宅すると我が家の玄関先に、まだ土のついたままの掘りたての筍が一本置いてありました。
筍が置いてあっただけでなく、土もまたたくさん落ちているのが、いかにも例年お届けくださる質朴なあの方らしい。そのこぼれた土がいかにも筍の新鮮さを象徴しているようです。 |
○ 向かふから兄呼ぶ声や捕虫網 大串 章・選 「百鳥」 掲載

むこうからあによぶこえやほちゅうもう
季語・捕虫網 夏
夏休みのこどもの兄弟のイメージ、弟であった作者自身の思い出でもあります。蝉、蝶、トンボ。
先に外に飛び出した弟の声が外から聞えて参ります。
「にいちゃーん、早く、裏の林にセミ捕りに
行こうよ。」 |
○ 説法の冥加のひとつ蚊に刺さる 中原道夫・選 「銀化」 掲載
せっぽうのみょうがのひとつかにささる
季語・蚊 夏
お寺の本堂で和尚様の話を聞いておりますと蚊が来ては手足を刺します。
早く長話を終わりにしてくれぬかなあ。有難い功徳のある説法だというが、蚊に刺されないですむ方策はないものか。
なんとまあ、説法を聞く冥加(=神仏の目に見えない助け、またそれによる得のこと)があるものよ、という皮肉ですな。 |
○ 炎昼に積まれ竿竹伸びてをる 中原道夫・選 「銀化」 掲載
えんちゅうにつまれさおたけのびておる
季語・炎昼 夏
| 真夏には竿竹売りのトラックが住宅地にやってまいります。「さおやー、さおーだけ。…」ていうやつです。この騒音を聞かされる人間様も暑さでうだっておりますが、その荷台で当の売られる竿竹も温度で膨張伸展もするでしょうし、気分もきっとノビテいることでしょう。 |
○ 星の名を諳んじをりぬ西瓜番 中原道夫・選 「銀化」 掲載 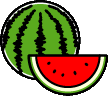
ほしのなをそらんじおりぬすいかばん
季語・西瓜番 夏
(従来は西瓜は初秋の季語)
西瓜番とはスイカを泥棒から守るため夜にスイカ畑で寝ずの番をする人のこと。古典的な世界のようですが、いまでも産地ではスイカがトラック一杯盗まれたとか報道があるので、収穫の直前には見回りしたりするようですね。
とにかく暇な仕事ではあるので、つい見上げる一面の夏の夜空の星の名にも詳しくなって諳んじることができます。人に問われれば、すぐに答えられます。「あれはアンタレス。それはスピカさ。」とかね。
|

 |