○ 春の土まう起こされてしまひけり 中原道夫・選 「銀化」
はるのつちもうおこされてしまいけり
季語・春の土 春

春の土は黒い、乾く、温かなイメージですが
いつまでも眠い春眠の感じを重ね合わせました。「土を起こす」とは鍬などで耕すことですが、ここでは春眠からの覚醒と二重意味化されています。
春の畑の土はまだ日を浴びてゆっくりと
眠っていたかったのに、もう耕されて
起こされてしまいましよ。 |
○ 登園をむづかりてをり花曇 中原道夫・選 新潟日報俳壇
とうえんをむずかりておりはなぐもり
季語・花曇 春 
幼児の保育園の行き始め、おうちを(〜つまりは母を)離れることがいやで、泣いたり、ぐずったりしがちです。花曇は桜の咲くころの暖かい、薄明るい雲り空の様子で、愁いの感じを伴います。春の登園はじめの頃ありがちな気候ですね。
公園には桜が咲いている曇り空の朝、こどもが登園に気が進まずぐずっていることですよ。
|
○ 濁されてやがて澄みけり春の水 中原道夫・選 「銀化」
にごされてやがてすみけりはるのみず
季語・春の水 春
雪解けの季節、春の温んだ田の畦の溜り水を歩くと泥が巻き上がり濁りました。しばらくするとまた元のように澄んで行きました。
悩まされることのあったわたしの心も 時間の経過とともに同様に…。 |
○ 初蝶の妻を呼ぶ間に消えにけり 黛 執・選 「春野」
はつちょうのつまをよぶまにきえにけり
季語・初蝶 春

春の陽気に初めて出現した蝶を初蝶と呼びます。ふつうは紋白蝶でしょう。
ただし虚子の句にこんなのも。
初蝶来何色と問ふ黄と答ふ 虚子
我が家の庭の菜花に初蝶が飛んできました。家人にも見せてやろうと、家の中に声を
かけました。そして振り向くと、蝶の姿はもう見えなくなっていました。
|
○ 歳月を揉みほぐす手や薇干 中原道夫・選 「銀化」
さいげつをもみほぐすてやぜんまいほし
季語・薇、薇干 春
山で採取したゼンマイを乾燥し、老女が茣蓙に座って揉みほぐしている晩春の風景。
実際はもちろんゼンマイを揉んでいるのです。句の焦点は皺の手、皺の薇。
老女はゼンマイを柔らかく、味をよく
するための揉みほぐしという単調な作業を
しながら思うのです。その嫁いで来た家や山村で過ごした年月のさまざまことを。
わたしには記念すべき、平成13年4月に新潟市で開催された第一回とねりこ句会での、中原道夫主宰の特選句でありました。
|
○ 保育器の中にも春の愁ひ顔 大串 章・選 「百鳥」
ほいくきのなかにもはるのうれいがお
季語・春愁 春
愁思に対しての春愁は情的とされます。ふつうのこどもには春愁なんてありません。でも保育器の中で育ちつつある未熟児の
顔はしわくちゃで、どこか哲学的なように見えます。
おや保育器の中で屈託なく育っているとばかり思っていた未熟児くんよ。小さな君にももう人の世の悩みはあるのかねえ。なんだか春の愁いのありそうな顔に見えるよ。 |

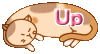 |